「家で全然勉強しない」
この悩みを抱えている保護者の方は少なくありません。
私は家庭教師や塾講師として数多くの中学生を見てきましたが、勉強しないのには様々な原因があります。
この記事では、中学生が勉強しない原因を7つ取り上げ、実際の指導経験に基づく解決法をお伝えします。
1. 何をやるべきか分かっていない

実は一番多いのがこのパターン。
何を勉強すればいいかが分からない。こんな子は「やらない」というより「やれない」という状態です。
-150x150.jpg)
宿題だけは最低限やるけれど、それ以外どうするか迷いますよね
① 宿題の丁寧さUP・・・正確に丸付けし、間違った問題は答えを隠して解き直す
② 今日習ったことをアウトプット・・・教科書やノートを見返し、授業で扱った問題をもう一度解く
③ スキマ時間に暗記・・・漢字、英単語、社会と理科の語句など短時間×回数をこなす
宿題を「やった」と「理解した」では勉強の質が全く異なります。
親は「勉強しなさい」と声をかけるより、「宿題が終わったら見せて」や「一緒の空間で勉強しよう」など質を高める働きかけがおすすめです。
2. 疲れて動けない
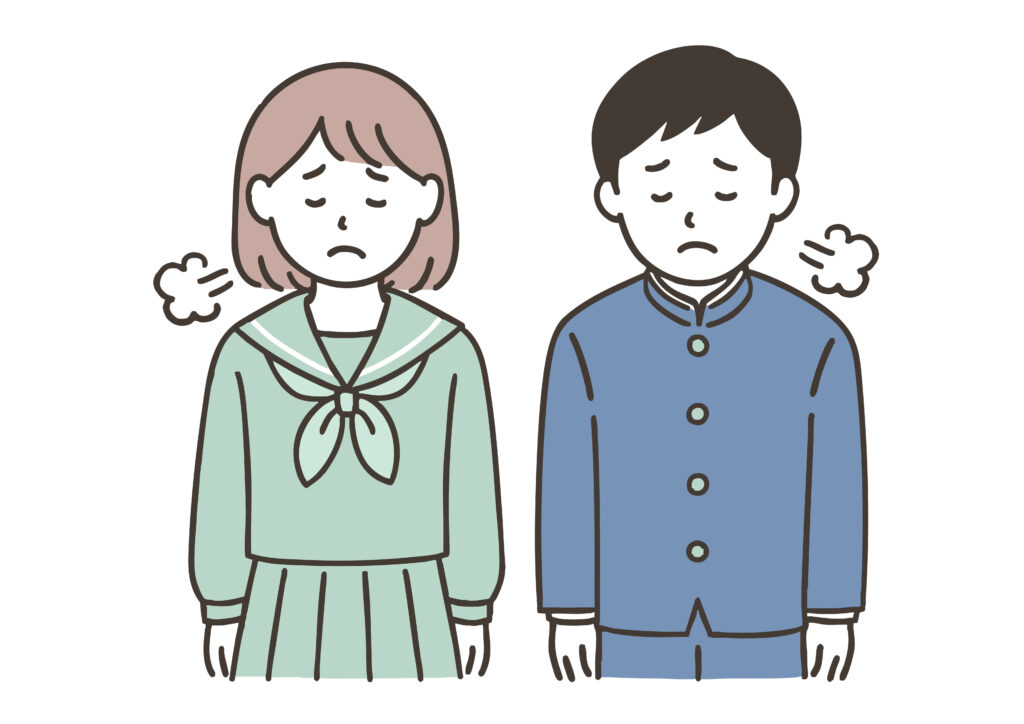
学校生活や部活、習い事で疲れて帰宅し、家に帰るとすぐ寝てしまうことはありませんか?
-150x150.jpg)
前日に夜更かしして、睡眠が足りていない場合も・・・
① 人の目が届くところで勉強・・・リビング学習や、学校の空き時間を活用する
② 食事、入浴、睡眠時間を確保・・・学校の授業に集中することを最優先で考える
③ スケジュール確認・・・この日は厳しい、この日は余裕があるなど確認し、勉強時間を調整する
家の中で勉強することも大切ですが、家の外(学校や塾など)で頭が働く状態になるよう生活リズムを整えましょう!
3. ゲーム・スマホ依存
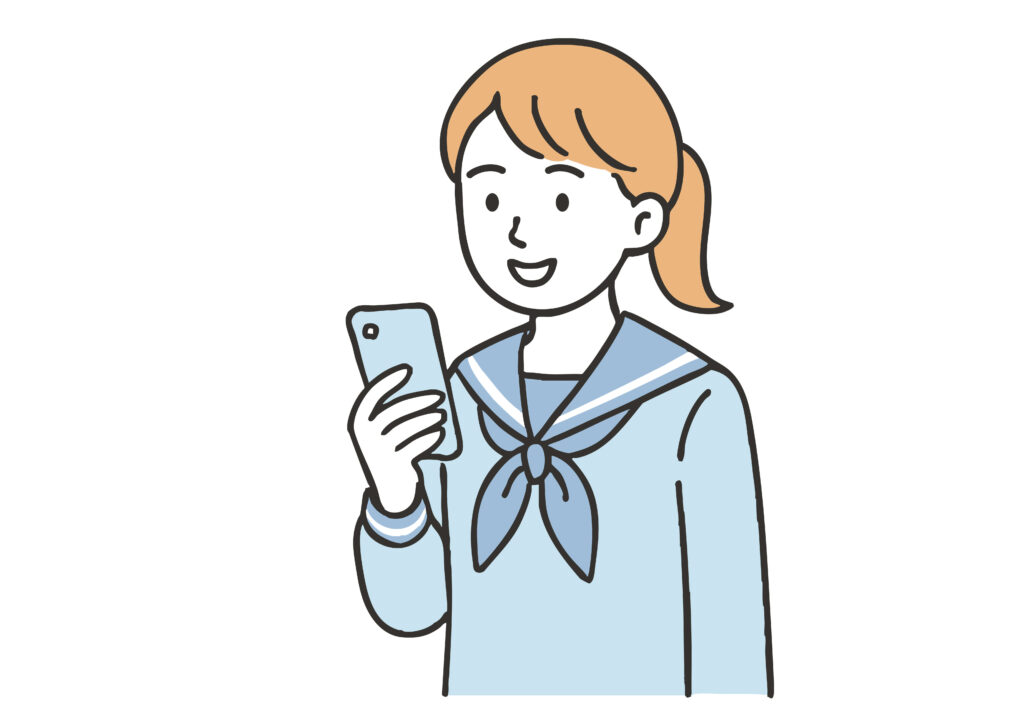
暇さえあれば画面を見て、注意しても聞かない。
子どもたちも自分の意思ではやめられない。それがゲーム・スマホ依存です。
-150x150.jpg)
口で言っても聞かないので、仕組みを工夫しましょう
① 終了時間を徹底・・・睡眠時間を削り、翌日に影響が出ることは絶対に避ける
② 勉強中は遠くに置く・・・遊び時間と勉強時間のメリハリをつける
③ 利用時間を見える化・・・スマホのスクリーンタイムやタイマーを使い、「使いすぎ」の自覚を持たせる
ルールは「家族で決め、家族で守る」ほど効果が出ます。
例えば夜◯時には全員リビングで充電するなど決め、大人が先にスマホを手放す姿を見せてみましょう。
4. なんとかなると思っている
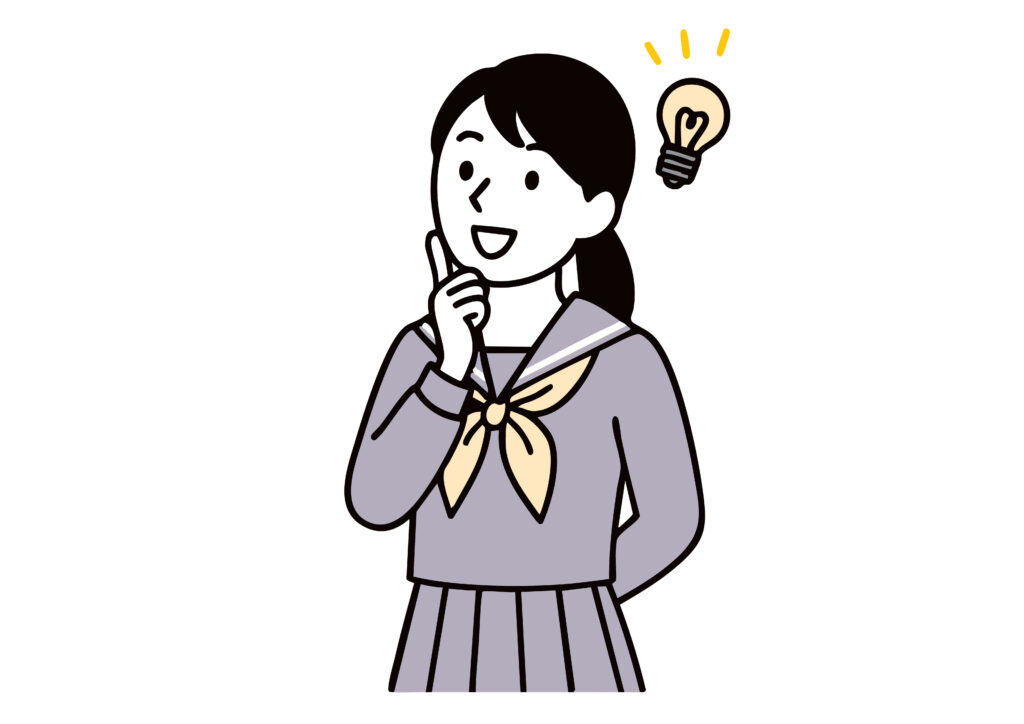
大人は過去の経験から「今勉強しないと後悔する」と考えますが、子どもには実感がなく危機感が持ちづらいものです。
「先のことなんて分からない」と投げやりになったり、「(親が)なんとかしてくれる」という甘えがあったりすることも。
-150x150.jpg)
情報は早く与えて損はありません!
① 家族で高校の話をする・・・自分の地域にどういう特徴の高校があるか知ることから始める
② 親の失敗談を話す・・・成功体験よりも失敗・苦労話の方が印象に残りやすい
③ 模試を受ける・・・塾などで年に数回開催。自分の立ち位置を定期的に確認する
情報を伝えたり、親の話をしたりしてもそれほど反応がないかもしれません。
しかし、子どものやる気や危機感はこのような経験が積み重なって初めて現れてきます。
「自分の人生だから自分でなんとかしていくんだよ」と地道に伝えていきたいものです。
5. 他に熱中していることがある

部活や習い事、趣味、恋愛、友達関係・・・。
勉強以外にエネルギーを注ぎたくなることもありますよね。
-150x150.jpg)
打ち込めるものがあるのはいいことです!
① 最低限勉強する習慣をつくる・・・「先に宿題を終わらせる」「◯分だけは勉強する」など達成できる分量で継続する
② 勉強のモチベーションにする・・・テンションの上がる音楽、文房具で勉強するなど工夫する
③ 区切りを決める・・・引退までは部活優先、◯◯のイベントまでは趣味を優先、など期限を決めてメリハリをつける
熱中していることが高校進学や将来につながることもあれば、自信になり、勉強モードに入ったときに頑張る原動力になることもあります。
6. 自己肯定感が低い

自己肯定感が低く「できないことはやりたくない」「やってもムダ」と考えてしまう子どももいます。
この場合、勉強を通じて成功体験を積ませていくことが必要です。
-150x150.jpg)
勉強という大きな括りではなく、細かく見ていきましょう!
① まず1教科、1単元を伸ばす・・・少しでも興味がある内容を重点的に取り組み「勉強が面白い、楽しい」という経験にする
② 数字以外の部分を評価する・・・休まず学校に行っている、宿題を自分からやる、字が丁寧、忘れ物をしないなどできている所を見つけて褒める
③ 親の学生時代の話をする・・・「勉強が嫌いだった」「◯◯が苦手で大変だった」という話を正直に伝える
特に社会や理科は単元が定期的に変わるので、気持ちを切り替えるチャンスが多い教科です。
また、自分に自信がない子どもの場合、個別指導でゆっくり丁寧に教えてもらうと心を開きやすい傾向があります。
7. プレッシャーが強すぎる

「勉強しなさい」という声かけから親子喧嘩が始まることはないでしょうか。
-150x150.jpg)
反抗期の子どもたちは、親の言葉には素直になれないことも・・・
① 指示ではなく確認する・・・「今日は何を勉強する(した)の?」と教えてもらう・見せてもらう
② テスト点数より準備過程を評価する・・・準備が足りなかった部分を確認し、改善を呼びかける
③ 第三者に相談する・・・学校の先生、塾や家庭教師などに間に入ってもらう
感情的に怒られている間、子どもの脳は「この時間を乗り切ればいい」と判断し、親が本当に伝えたいことは全く届かない状態になっています。
子ども対して心配し、サポートはするもののプレッシャーをかけすぎないことがポイントです。
勉強しない子が変わったきっかけ(実例)
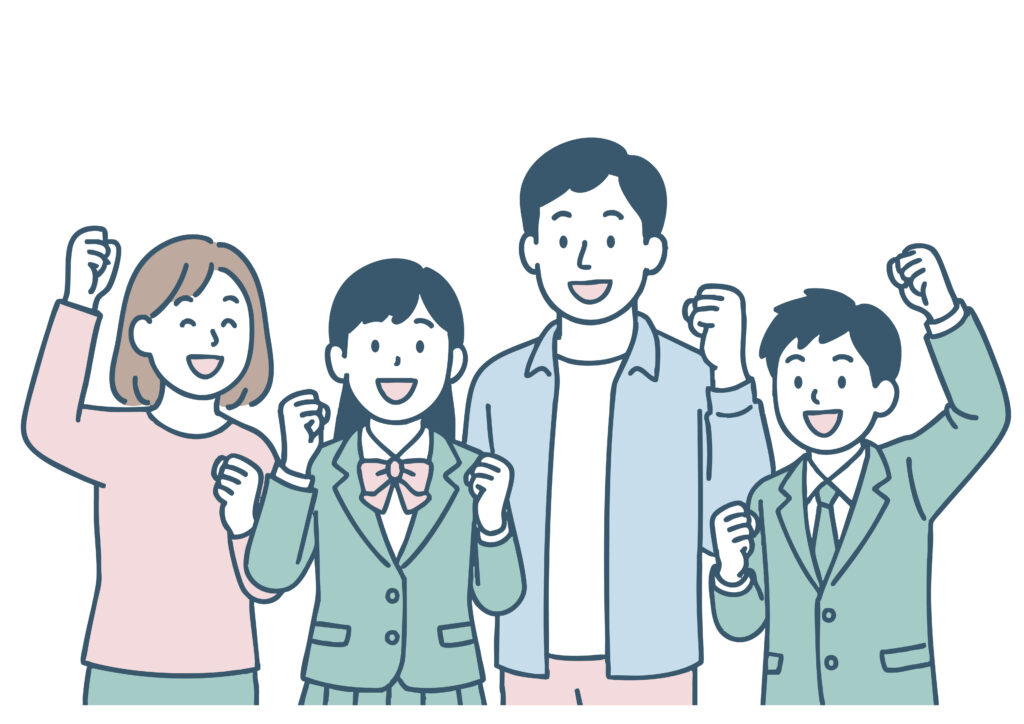
勉強しない子が変わったきっかけを紹介します!
・好きな人、友達と同じ学校に行きたい
・部活を悔いなくやり切った
・家庭教師や塾で「分かる」が増えた
・負けたくないライバルができた
・親が同じ空間で勉強、仕事をするようになった
・学年が変わるタイミングで自然と
・高校のことを知って興味を持った
変わるきっかけは人それぞれ。一気に変わる子もいれば少しずつ変わっていく子もいます。
-150x150.jpg)
行きたい高校が見つかり、突然「合格するまでスマホは封印」と宣言した生徒もいました!
中学生が勉強しない原因まとめ
中学生が勉強しないのは、以下の理由があります。
- 何をやるべきか分かっていない
- 疲れて動けない
- ゲーム・スマホ依存
- なんとかなると思っている
- 他に熱中していることがある
- 自己肯定感が低い
- プレッシャーが強い
子どもの勉強の悩みは、保護者にとっても大きなストレスになりますよね。
完璧な対応でなくても、子どもが勉強しない理由に合わせてサポートすることで何か変化があるかもしれません。
今回の記事が1つのヒントになれば幸いです。
また、第三者のサービスを使うことは、成績や子どもの気持ちを変える大きなチャンスになります。
保護者面談や無料体験を通じて信頼できる塾・家庭教師を探してみてください!

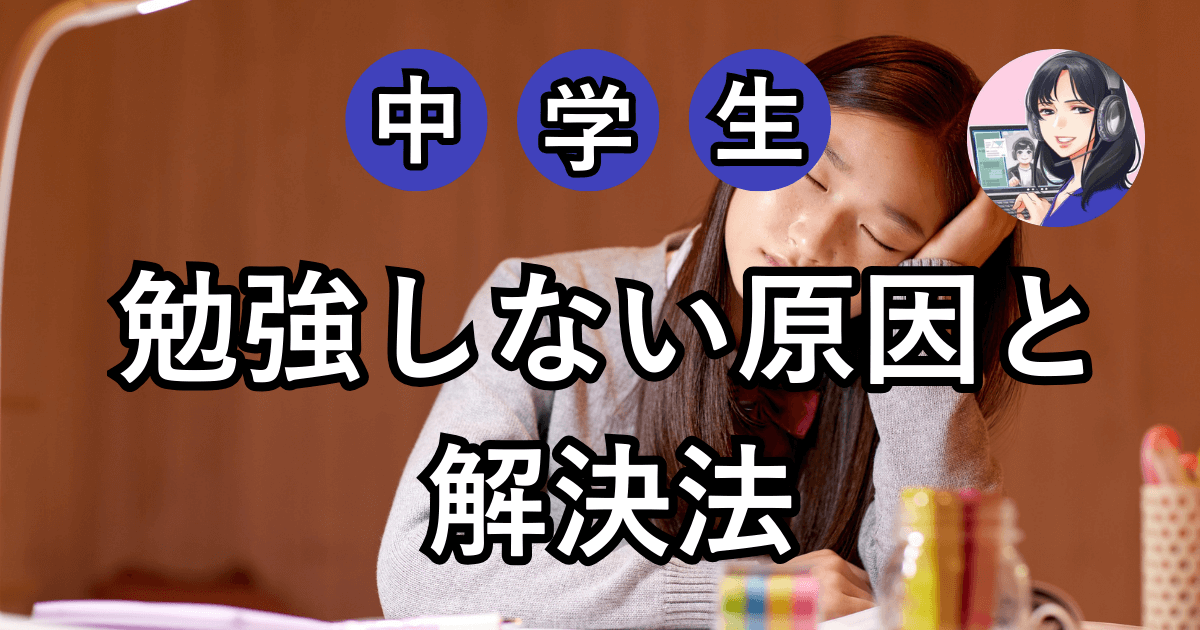

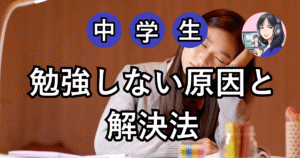
コメント