「定期テストでなかなか点数が上がらない」 「正しい勉強法を知りたい」という中学生や保護者の方は多いのではないでしょうか。
今回は、塾講師や家庭教師として数多くの生徒を見てきた経験から、 実際に点数を伸ばした生徒の勉強法 を整理しました。
-150x150.jpg)
今日から取り入れられる工夫も多いので、ぜひ参考にしてください!
1. テスト勉強はいつから始める?

テスト勉強は「範囲表が配られてから」「部活が休みに入ってから」始めるという生徒も多いですが・・・
実は、テストが終わった直後から次のテストを意識することが理想です。
-150x150.jpg)
テスト後に習う内容は、ほぼ間違いなく次のテスト範囲になりますよね!
「いつも好成績の人」はテストが終わっても、授業や宿題、小テストにしっかり取り組みます。
テスト前に慌てて勉強している人は、普段の勉強の「丁寧さ」を意識してみてください!
2週間前からは「テストモード」に完全に切り替えましょう。
①テスト範囲のワークを進める
②授業のプリントを整理整頓する、空欄を埋める
③「ここはテストに出す」という情報を集める という3つの動きが必須です。
2. 科目別の勉強法

英語・数学(積み重ね型)、社会・理科(暗記型)、そして国語、それぞれの勉強ポイントを紹介します!
英語・数学
- 英単語テストは常に満点を目指す
- 英語の教科書を音読し、訳せるか確認する
- 数学の分からない問題はその日のうちに質問
- 数学は教科書の例題・演習問題をテスト前に解き直す
-150x150.jpg)
日々の「分からない」が溜まると、テストに間に合いません💦
小さな努力の積み重ねが大きな差につながります!
社会・理科
- 教科書を音読する
- 教科書の太字を赤シートで隠せるようにして暗記する
- スキマ時間にアプリで復習する
- 学校ワークを複数回解く
-150x150.jpg)
暗記は短時間×日数をこなしましょう!
国語
- 学校ワークの「漢字」「文法」のページを反復
- 学校ワークの読解問題は、答えを見ながら丸写しするのではなく、答えを覚えてから書き写す癖をつける
- 教科書を音読する
-150x150.jpg)
国語は読解力を課題とする前に、「漢字」「文法」の暗記が後回しになっていないか確認しましょう!
5教科に限らず中学生の学習法や教育に役立つ本が気になる方は、この記事を見逃しなく!
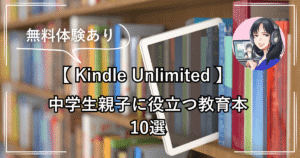
3. ワーク・教材の使い方
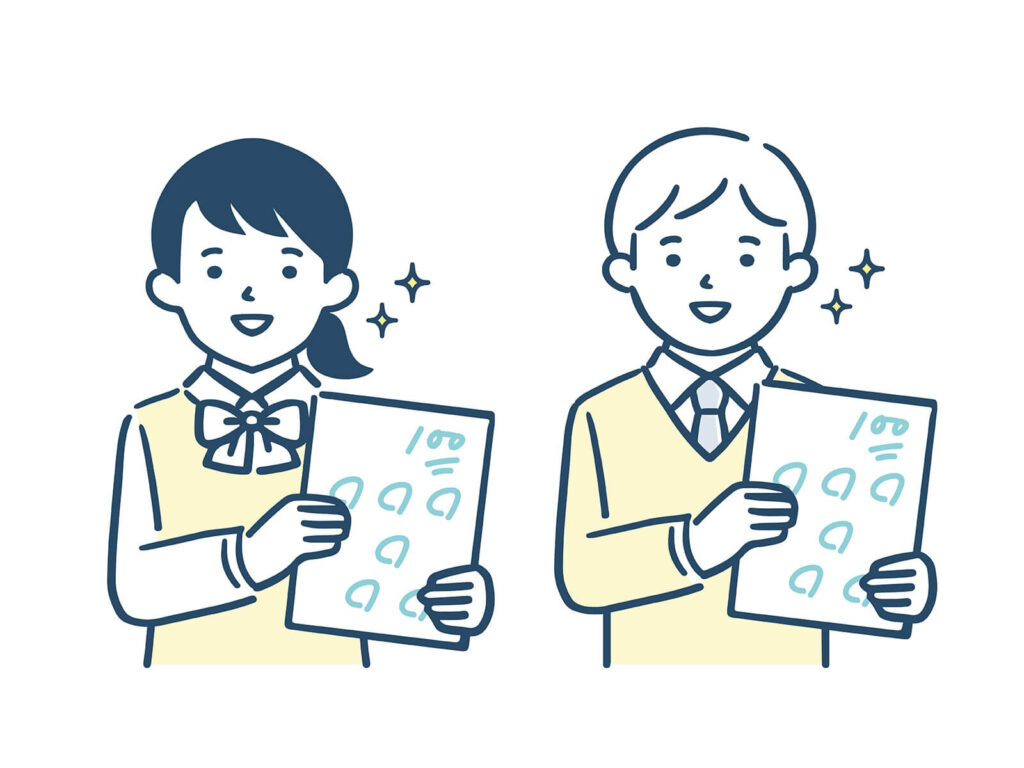
学校ワークは「3周」が基本
私が勤めていた塾では「テスト勉強の基本はワーク3周」が合言葉でした。
- 習った直後に1回目
- テスト範囲表が出たら2回目
- 間違えた問題を重点的に3回目
塾や家庭教師の先生と意見交換する場でも、ほぼ毎回ワークの話題が上がります。
-150x150.jpg)
ワーク1回で終わっている生徒が多く「もったいない」と感じています💦
一気に3回に増やすのがきつい場合は、ワークの取り掛かり時期をできる限り早めましょう。
(学校で指示される前にワークを解き、怒られたという話は聞いたことがありません。不安な人はノートに解けばOKです)
教科書は汚してなんぼ
この「汚す」は書き込む・線を引く・折り曲げることを指します!
例えばサッカーの試合で、ユニフォームが汚れることを恐れる選手はいないはず。
しかし教科書を含め勉強教材についてはなぜか、「白いまま」を保とうとする傾向が見られます。
-150x150.jpg)
無我夢中で勉強していることが伝わる教科書は、かっこいい!
学校の授業ではプリントを使うから教科書はほぼ開かないという話も聞いたことがありますが、学校で使わないなら家でフル活用しましょう!!
授業プリント・ノートは見返すもの
授業プリントやノートには、学校の先生の「重要ポイント」がつまっています。
プリントやノートに書くだけで、全てが頭に入る生徒なんていません。
ワークを解く前に見直したり、 教科書と同じように書き込みをしたり、何度も使うようにしていきましょう。
-150x150.jpg)
ノートを取る段階で重要語句を赤ペンで書き、赤シートで消せるようにする工夫もおすすめです!
5. モチベーション維持のために

生徒自身の工夫
- 目標点を決める(取れる点数ではなく取りたい点数)
- 何をすべきか見える化する(範囲表を机に貼る、計画表は常に開いた状態にしておく)
- やる気が出てまで待つのではなく先に行動する(勉強机に座る、教材を取り出す)
保護者のサポート
- 「勉強しなさい」と声をかけすぎない
- テスト2週間前からは大きな外出予定を減らす
- 書店に一緒に行く(本人が選んだテキストがあれば買う)
- テスト後は点数よりも勉強の仕方を振り返る
6. 成功例と失敗例

ここからは、私が実際に見てきた「成功例」「失敗例」をリストアップして紹介します。
成功例
・黒板を写すだけでなく、先生の一言もノートにメモしている
・教科書やプリントを赤シートで隠して何度も復習している
・ワークで間違った問題に印をつけ、苦手が一目で分かるようにしている
・疑問があるところに付箋をつけ、すぐに質問できるようにする
・テスト前2週間になったらスマホを封印する
指示を素直に聞いて実行する生徒は成長が早いです。また、「何度も繰り返す」前提で日頃から勉強しています。
失敗例
・授業で寝ている
・学校ワークは提出日ギリギリ
・授業プリントやノートが揃っていない、空欄が多い
・試験範囲を把握していない
・丸付けが適当
・暗記物を見るだけで覚えようとする(覚えたか確認テストすることが重要)
・徹夜で乗り切ろうとする
思い当たる節があった人も大丈夫。「これはよくない」と気づいたら、今日から改善していきましょう。
中学校の定期テストで結果を出すために:まとめ
勉強しているつもりの生徒でも、実はやるべきことができていないケースはよくあります。
定期テストで成果を出すのに裏技はなく、 「日々の勉強意識」と「学校教材の活用」が一番の近道です。
・テストが終わった直後から次のテスト勉強は始まる
・学校ワークは早めに取り掛かり、複数回解く
・暗記物は短時間×日数の積み重ね
正しい勉強法を身に着け、力をつけていきましょう。
今後も、中学生の勉強に役立つ情報を発信していきます!
自分でできるところまで勉強した上で、レベルアップするには塾や家庭教師が必要だと感じる場合はこちら
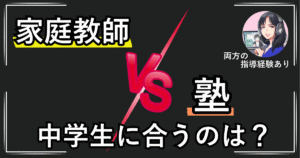

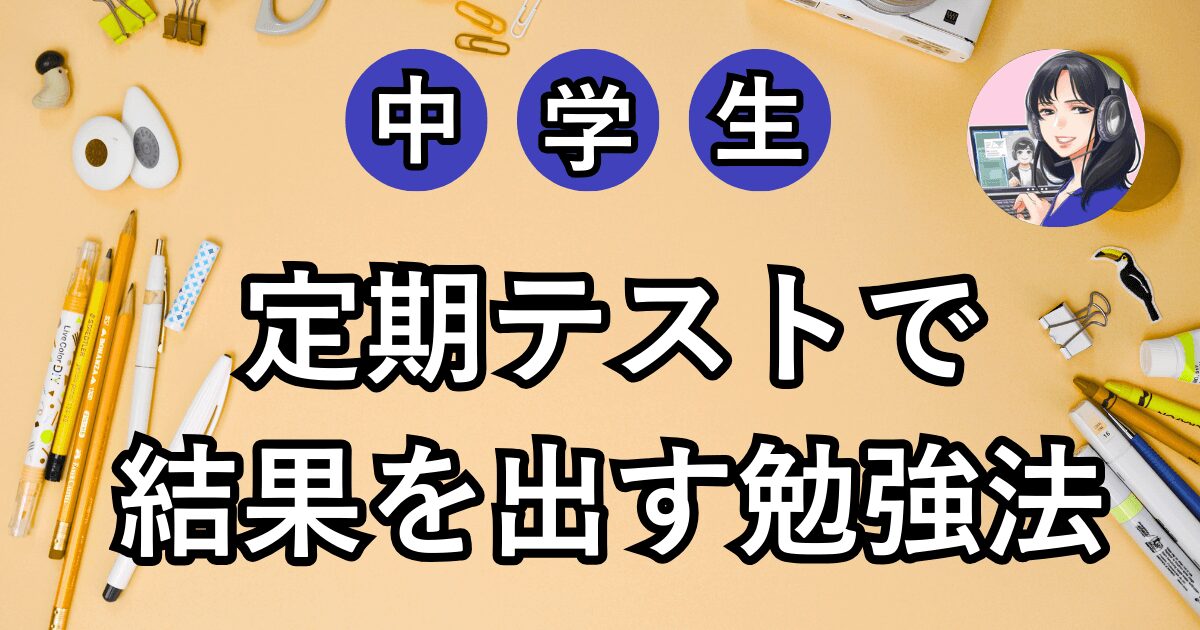

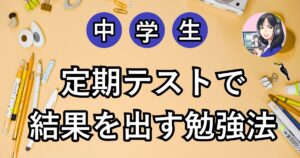
コメント